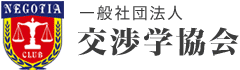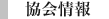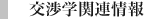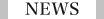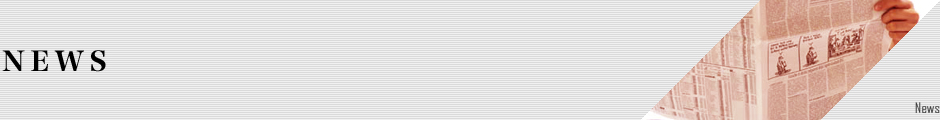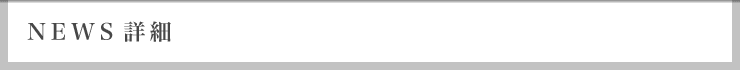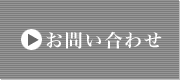2015年9月11日
“いじめ対策”に「交渉学」。那須で小学6年生に交渉学の授業を実施しました

「交渉学」とは、交渉学=問題解決のための「対話の思想と技術」の体系 。
“いじめ”が、相手を理解しようとせず、相手を攻撃することだとするなら、「交渉学」の智慧は、“いじめ対策”にとても役立ちます。
「交渉学」が大切にしている三つのバランスの中でも「相手と自分 のバランス」に通じるところです。
2015年9月11日(金)、交渉学協会理事長 田村次朗は、文部科学省委託事業である「那須塩原いじめ対策コンソーシアム」の活動と連携して、小学6年生向けに「交渉学」の授業を展開しました。
授業2時間分を使った授業に子どもたちも集中して参加しました。
「こんなに頭を使った授業はなかった。自分や相手が話していることを、“どんな意味があるのか?”と考えたことはなかったから、とっても頭を使った。すごく楽しかった」(サッカー少年談)
「興味あることには全力で取り組むようにしているです。面白かった!こんなにノートを書いちゃいました」(バスケ少年談)
企画に関わった慶應義塾大学4年生の小林さんは、「これからの世の中はみんなで、新しい答えを創り上げていく社会。小学生のころから相手の意見に耳を傾け、相手を理解しようとする気持ちが育まれれば、いじめは勿論のこと、社会の不条理に対して立ち上がる人が増えると思う。共創社会にむけて、とても大切な授業であり、彼らの未来につながる授業だと感じた」と感想を語ってくれました。
交渉学協会は、「実践交渉学認定プラクティショナー」の養成をはじめました。認定プラクティショナーには、仕事や生活の実践を通じて「交渉学」を活用いただきながら、機会があれば、こうした教育の現場で「生きた交渉学」を伝えていただきたいと考えています。
協会では、学校向けのプログラムを用意しています。
多くの方に「認定プラクティショナー」になっていただき、一緒に「交渉学」を普及させていきたいと思います。
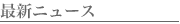
2021年11月19日
2019年6月15日
2019年2月22日
東京弁護士会法友会にて三方よしのコミュニケーション【実践交渉学 特別講座】講習で登壇
2018年6月20日
交渉学協会認定「交渉学プラクティショナー」が新たに2名誕生しました。
2018年4月30日